子育ての秘訣
考える力を養う
やわらかな発想をわが子に
子どもの本嫌いには2つのタイプがあります。本そのものが嫌いな子どもと、読む気はあるのに根気が続かない子ども。読書は考える力の基礎になります。ではどうしたら子どもの本嫌いを治せるのか、ご一緒に考えて見ましょう。
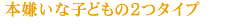
「うちの子は本が好きではないようです」「本を読んでもすぐに飽きてしまいます」といったご相談を受けることがよくあります。詳しい話を聞いたり、実際に会ってみたりしたところでは、こうした子どもに2つのタイプがあるようです。
一つ目は、読書を無理強いしたり、読みたくも無い本を与えられるなどで、本そのものが嫌いになってしまった子ども。言わば大人のおしつけで読書嫌いになったケースです。この場合は対処の仕方があります。
○とにかく楽しみのために読書させる
○好きな本を選ばせて、親は文句を言わない
○読んだ後に内容について質問をしない
○感想を聞かない、感想文を書かせない
こうしたことに気をつければ、再び自分から読み始めるでしょう。
けれども本が嫌いではないのにギブアップしてしまう二つ目のケースの原因はこれとは違います。

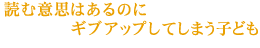
こんな子どもに好きな本を持っておいでと言いますと、お気に入りの本を持ってきます。けれども 年齢にしては、少し幼い内容の本を持ってきます。例えば小学1年生ですが、文字の少ない絵本を選びます。
試しに「読んでごらん」と言うと、読み方がたどたどしいのです。絵本は基本的にひらがなで書かれているので、漢字のように一瞬で単語を認識することができません。
「あ・め・ん・ぼ」と読んで「あめんぼ」のことだと理解します。こうした読み方なので時間がかかるのです。年齢相当の子ども向け物語を声を出して読んでもらうと、単語や言い回しが理解できていない部分でつっかえてしまいます。
それを繰り返しているうちに、「ぼくこの本読むのやめる」とギブアップしてしまいます。
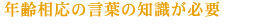
こうした子どもは繰り返し読ませたら、スラスラ読めるようになるのでしょうか。繰り返し読むことが苦痛でそれはできません。また発音できることと理解することは別ものでもあります。
小学生では簡単な漢字の読みのテストをしてみると、訓読みに比べて音読みが苦手なことがわかりました。普段使うことの多い訓読みは覚えやすく、音読みは書いた文章に出てくることが多いからです。
これらの様子から自分が知識として持っていない言葉を読むことが難しいのではないかと推測されます。要するに語彙が不足していると、読書が苦手となってしまうわけです。

語彙を補ってあげれば絵本から物語へと、読む本をステップアップしていくことができるはずです。どんなことをしたら良いのでしょうか。
○家庭の会話を増やす
家庭では「ごはんよ」「はーい」に代表される問いかけと応答だけの会話が主流となりがちです。けれども子どもは会話から新しい言葉を学んでいきます。
テレビや新聞で今話題のことが出てきたら、それを元に子どもとお話をしてみましょう。少し意識してきちんとしたセンテンスで話すようにしてください。兄弟姉妹がいる場合に、下の子がませるのは兄弟の言葉を早く身につけるからです。親子の会話でも語彙が増やせます。
○物語を読み聞かせる
ストーリーに興味をもたせ、物語の言い回しに慣れるために読み聞かせが大切です。年齢より少し上の子どもが対象の物語を読み聞かせてやると効果的です。
同じ本を何度も読んでとせがまれたら応じてやりましょう。繰り返し聞くうちに暗記する子どももいます。うっかり間違うと、その点を指摘されてしまいます。こうなればしめたもの、親がいない時に続きが知りたくて、自分から読み始めたりします。
○言葉をたくさん投げかける
ま
だ自分では本を読まない赤ちゃんでは、おしゃべりできなくても言うことはかなり理解できます。たくさん言葉をかけてあげてください。脳は繰り返しの刺激でシナプスのネットワークが強化されます。沢山言葉をかけてやると、おしゃべりするころにアウトプットとなって返ってくることでしょう。
○読書の環境を整える
幸いにもまだ子どもに読書を無理強いしていなかったら、読書する環境を整えることから始めたいもの。本棚にある程度の本をそろえます。子どもが読みたいと思った時、すぐ手に取ることができるように。
新品を購入しても良いですが、古書店で買っても構いません。読んでも読まなくても、毎週図書館で10冊借りてくるという方法もあります。
親が読書する姿を見せることも環境のひとつです。書道家の相田みつを先生も、かつて同じような相談を受けた際に「お母さん、あなたが本を読んでいなくて、勉強しないから子ども達もそうなんだ」と言ったそうです。
親が読んでいる→なんだか面白そう→本を読むまねをする→読んでみたら面白い→本が好きになる
こんな良い循環が起きる環境が理想です。
羊(2009/10/16)
